

![]()
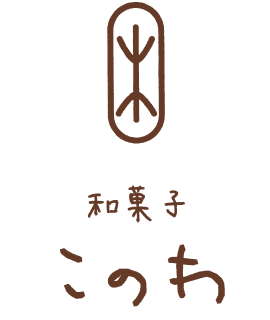
和菓子職人として、お菓子を作るだけでなく、自ら食材を育てるところから始めたいと思うようになり新規就農して3年。これまでに培ってきた農業への考えが少しずつ形となり、手応えを感じ始めた今、私が歩んできた道のりをお話ししたいと思います。
1年目の春に黒豆や大豆、小豆を少量ながらも栽培してみることにしました。初めての穀物栽培で気づいたのは、育てることの大変さと同時に、その尊さでした。手作業で収穫していた昔の農家の方々の苦労を想像し、現代の農法が石油に大きく依存していることに危機感を抱きました。「もし石油が途絶えたらどうなるのか?」そんな不安を胸に、自分の店で使う穀物だけでも自給できないかと模索し始めたのです。
次の年には、さらに挑戦を広げ、古代小麦であるスペルト小麦を栽培することにしました。収穫した小麦は足踏み脱穀機と手動の唐箕で丁寧に選別し、自家製粉で全粒粉にしました。その粉を使ってどら焼きを作り、関係者の方々に試食してもらったとき、私は市販の小麦粉に負けない品質と、何よりも「自給できる」という安心感を得た喜びを感じました。これこそが私の目指す方向なのだと、心が確信に満たされた瞬間でした。
5月の連休後、私はついに水稲(夢つくし)の栽培にも着手しました。約300坪の田んぼを鍬とスコップ、グラウンド整備用の道具で一人で整地し、田植えは地元の農家さんの協力を得ながらなんとか進めることができました。しかし、稲刈りの際に使ったバインダーという機械が度重なる故障に見舞われ、何度も作業が中断してしまいました。そのたびに、近くの農家さんが手を貸してくれ、無事に収穫を終えることができました。稲を天日干しで乾燥させ、手間をかけながら脱穀し、ようやく炊き立てのご飯にたどり着いたときの喜びは、今でも心に深く残っています。
そんな中でふと、「自分は手作業にこだわっていたはずなのに、今では機械と石油に頼っている」と気づきました。最初はすべてを手作業で行おうとしていましたが、炎天下での作業を他の方に手伝ってもらうことが難しく、私一人ではどうしても機械の力を借りなければならなかったのです。この選択が、自給への道を続けるための大きな転機となりました。
やがて、世間では米不足のニュースが流れ始めました。そんな時、私は「自立して自給する力を持つことの大切さ」を改めて痛感しました。水や食料、エネルギーといった生きるために不可欠なものが、不作や災害、紛争によって不足する未来が訪れるかもしれない。私たちは今、時代の大きな転換点に立っており、どんな時でも自分の力で最良の選択をし、自立した生活を送る必要があると強く感じています。
私が6次産業化を進める目的は、穀物を作ることそのものです。店舗の規模を無理に大きくすることはせず、この仕組みを通して、自分で選択肢を持ち続け、何があっても揺るがない生活を目指しています。こうした考えを少しずつ和菓子にも取り入れ、店のショーケースには新しい取り組みから生まれた和菓子が並ぶようになりました。
例えば、「きなこもち」は、自家栽培と自家製粉で作った玄米粉のお団子に、シンプルにきなこをまぶした一品です。この商品は、自給への新たな一歩を象徴する和菓子となりました。また、「全粒粉のどら焼き」は、私が手塩にかけて育てた古代小麦から作られ、限定品としてお客様に提供しています。そして、期間限定の「芋ようかん」は、自家栽培の鳴門金時を使い、シンプルな材料で仕上げた甘さ控えめの一品です。
こうして、私は和菓子作りを通じて、食材の栽培から手掛けることに価値を見出し、自立と自給の道を歩んでいます。
いつの日もオンリーワンの和菓子このわであり続ける為、6次化を加速させ当店にしか出来ない強みを構築して参ります。