

![]()
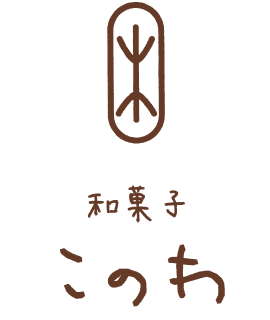
「デルモンテ破産に見る、“商売”の終焉と始まり」
⸻
米デルモンテ・フーズが、創業138年の歴史に幕を下ろしました。
かつては“缶詰王国”とも呼ばれ、世界中の台所に、安心と保存の知恵を届けてきた存在です。
缶詰というのは、本来とても尊い技術です。
保存が難しい時代に、遠く離れた人のもとへ食べものを届けることができる。
災害や困難な時に、命をつなぐ備えにもなる。
農作物の余剰を捨てることなく、食として活かし続けられる。
つまり、缶詰を大量に生産することは、本来“人々の暮らしを支える素晴らしい営み”だったのです。
⸻
ではなぜ、そんな企業が破産という道をたどったのか。
理由はひとつではなく、はっきりと断定もできません。
でも確かなのは、“本来の目的”と“現代の構造”が、どこかですれ違ってしまったこと。
誰かの暮らしを支えるための技術が、
いつの間にか“数字”を生む手段になり、
規模を追い、効率を追い、利益を追い続ける中で、
「なぜ作るのか」が置き去りになっていったのかもしれません。
⸻
この出来事は、単なる企業の経営破綻ではありません。
それは、「商売でお金を稼ぐ時代」が静かに終わろうとしているサインだと、私は感じています。
人々はいま、もう一度問い直し始めています。
「誰が、なぜ、それを作っているのか」
「この商品は、自分の暮らしとどう繋がっているのか」
価格よりも共感を。
利便性よりもつながりを。
大量よりも、必要なだけ。
⸻
「売る」ことより「届けること」
「稼ぐ」ことより「満たすこと」
「流通」より「循環」
そんな価値観が、少しずつ、でも確かに広がりはじめています。
⸻
いま私たちが目の前で体験しているのは、単なる経済の変化ではなく、“価値”の転換です。
“商売”というしくみが一度解体され、
もう一度、人の手と心で「営み」として立ち上がろうとしている。
大きな時代の潮目の中で、
私たちは、ただ静かに問われています。
「それは、誰のために、何のために作られたものですか?」
⸻
必要とされる人に、
必要な分だけ、
まっすぐに届く。
それだけで十分だった。
本当は、最初からずっと。