

![]()
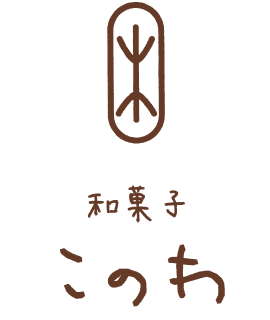
価値の循環と生き残る道
このグラフを見てください。
紫=M1(銀行が民間に貸しているお金)、青=M2(日本にある全ての現金と預金の総額)、緑=GDP(経済成長率)、赤=国債残高(国の借金)、グレー帯=コロナ期です。
お金は増えているのに、私たちの暮らしは楽にならない。
それはなぜか─
⸻
価値とは何か
社会には大きく分けて二つの価値があります。
直接的な価値:食料を育て、物を届け、生活を支える
象徴的な価値:希望や安心を与え、人の心を支える
例えるなら──
直接的価値=お米
象徴的価値=果物
ここで大切なのは、価値=価格(お金)ではない ということです。
⸻
お金の側で起きていること
最近、私たちは「物価が高い」と感じます。
けれど実際に変わったのは、物そのものの価値ではありません。
コロナ禍で飲食店に支払われた1日6万円の時短協力金。
お店が閉まっていても、お金だけは増えていきました。
グラフを見れば、その結果どれほどお金の量が膨らんだのか一目瞭然です。
「働かずにお金が増える」状態が続けば、お金の価値は薄まり、
同じ物により多くのお金を払わされる──つまりインフレです。
そしてこの世の中では、直接的・象徴的価値の大小に関係なく、
「お金をたくさん持つ人」こそが最も有利に働く仕組み になっています。
結果として、お米も果物も同じように値上がりしていくのです。
⸻
景気の流れと価値の使われ方
経済の波によって、人がお金を使う対象は変わります。
景気上昇期:りんご・メロン・桃といった「象徴的価値」にお金が流れる
景気後退期:お米や水道光熱費といった「直接的価値」にお金が集中する
つまり──
お米が売れる時は、果物は売れづらい
果物が売れる時は、お米の値段が下がりやすい
今はまさに、景気上昇期から後退期へと移行している最中です。
⸻
これから残る仕事の仕方
お金の価値が下がってきた今でも、生きるためのお金は必要です。
では、どんな働き方をすれば生き残れるのでしょうか。
まず残るのは 一次産業。
米や野菜を育て、水を確保し、命を支える仕事。
お金の価値が下がっても、これらは「生きること」そのものだからです。
しかし一次産業だけでは立ち行きません。
消費者が購買意欲を失えば、どれほど良い作物でも「買える価格」でなければ需要は崩壊するからです。
だからこそ──
価値が変わらないまま、むやみに価格を上げてはいけない のです。
今必要なのは、生産から加工、販売までを一貫して担う六次産業化の形。
すべてを自ら抱えることで固定費を抑え、
消費者が買いやすい価格で価値を届ける。
この仕組みこそが、これからの時代に
「生きること」と「お金を稼ぐこと」を両立させる唯一の道 です。
⸻
これからの指針
お金はあくまで道具。
価値は、人と人とのつながりや支え合いの中にあります。
だからこれから私たちに必要なのは──
直接的な価値を担う人を尊重すること
象徴的な価値を生む人を認めること
そして「生きること」と「稼ぐこと」を分けて考える勇気を持つこと
⸻
結び
和菓子このわは、その両方を担いながら、
小さな港として「生きること」と「稼ぐことのバランス」を示し続けます。
楽してお金を稼いでも、
物質的価値(直接的価値や象徴的価値)が伴わない社会は続かない。
お金だけが増えても、米も果物も増えない。
お金だけが回っても、笑顔や信頼は生まれない。
だから今の社会は「豊かに見えて、実は痩せ細っている」。
グラフが示す通り、お金と借金だけが膨らみ、
価値を生む力は置き去りにされているのです。
9月1日、このわは14周年を迎えます。
お金ではなく、価値そのものを循環させる。
和菓子このわ3.0の世界へ。
全ては生きる為に。
光のさすほうへ──
ここまで読んでくださったあなたに、心から感謝します。
これからの世の中、どんな事があろうと楽しく豊かに暮らしていきましょう。