

![]()
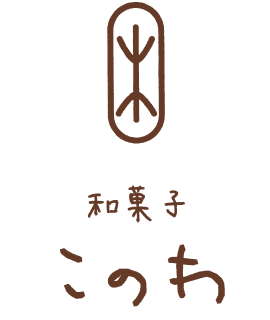
一方通行の終焉と、循環のはじまり
人はいつから、
「生きること」と「稼ぐこと」を
別々に考えるようになったのだろう。
かつて人々は、
自らの手で米を育て、味噌を仕込み、
季節の恵みを分け合いながら暮らしていた。
そこには、つくる人と食べる人の境界はなく、
「働くこと」も「感謝すること」も、
同じ循環の中にあった。
けれど、
産業が発達し、効率が最優先される時代になると、
人は土から離れ、「つくる」を他人に委ねた。
その瞬間、経済の歯車は回り始め、
「お金」は感謝の印から、
“得を競うための道具”へと姿を変えた。
やがて都市は膨張し、
ボタンひとつで何でも手に入るようになった。
その便利さの裏で、
人は“待つこと”も“育てること”も忘れた。
心が通う前に、モノが届き、
感謝の前に、消費が終わる。
それが、今の現実。
国がどれだけお金を発行しても、
循環しない社会では“幸せ”は増えない。
なぜなら、
豊かさとは「量」ではなく、「流れ」だから。
⸻
では、どうすればいいのか。
その答えは、
昔から人々の暮らしの中にあった。
お茶の木が人を迎え、
シュロが家を整え、
味噌を仕込み、米を分け合う。
秋には柿を干し、春にはよもぎを摘む。
その暮らしの一つひとつが、
“生きること”の原点だった。
誰かが作り、誰かが受け取り、
また誰かが返す。
そうして「恩」は形を変えながら巡っていた。
⸻
和菓子このわは、
この循環を、もう一度確かな形として取り戻したい。
今年のお米作りは、
脱穀、籾摺り、精米、貯蔵まで、
すべて自分の手で完結させた。
二、三年前。
缶コーヒー一杯さえ惜しみ、
水筒にインスタントコーヒーを入れて働いていた。
あの頃、消費を限りなく捨て、
“次に繋げ、生み出す仕組み”に、
すべてを投じた。
そして今、
お米作りを自分の手でやり遂げたことを、心から誇りに思う。